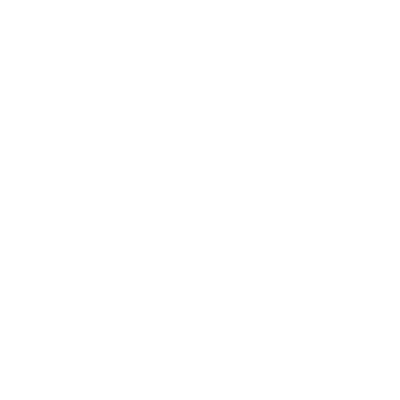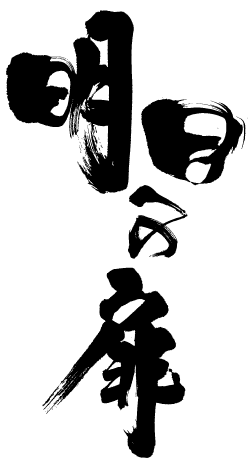動画を見る
全ストーリーへ
動画を見る
全ストーリーへ
 動画を見る
全ストーリーへ
動画を見る
全ストーリーへ
加賀竿職人
中村 直人
Nakamura Naoto
1998年 富山県生まれ
幼少期から釣りが大好きで、小学生の時に初めてドブ釣り※を経験する。中学生の時はすでに釣り道具を自作するようになっていた。
大学に釣りサークルがなかったため仲間を集めてサークルを立ち上げ、釣りに没頭する日々を送る。
その頃、釣りの歴史や文化も積極的に学んでいて、その過程で加賀竿の存在を知り、伝統的な竹製の鮎釣り竿の製法を受け継いでいる加賀竿職人の中村滋さん(白峯)のもとを訪ねる。
その時見た竹製のドブ竿に感動して、弟子入りを決意。2021年に通い弟子として入門する。
タナゴ竿や鮒竿などを制作しながら、修業を続けている。
※ ドブ釣り・・・鮎釣りのうち、流れの緩やかな川で毛針を用いた釣り方を指す。
伝統の守り手
和竿は一見すると作り方も似ていて機能的にも変わらないように見えて、実は、その地域の文化や歴史が成り立ちに大きく影響しています。
加賀の他にも竹製の伝統的な和竿の産地はあるのですが、加賀竿を学びたいと思った理由は、やはり「生まれ育った北陸の伝統を守りたい」という気持ちが強かったからです。
師匠を訪ねて、初めて加賀竿を見た時は「竹がこんなにも美しくなるのか」と衝撃を受けました。
師匠はたった一人で加賀竿の伝統的な技法を守り続けている。
今は修業中の身ですが、少しでも早く加賀竿職人だと周りの人に認められるようになりたい。それが加賀竿の伝統的な技法を守ることにもなると思っています。全ての時間を加賀竿の技法を学ぶために捧げています。
「一貫制」の楽しさ
竿作りはお客様から要望を聞いてから完成まで一人の職人が行います。
どの工程が重要なのかとよく聞かれるのですが、全ての工程が難しく、一つのミスが取り返しのつかないことになってしまうのが竿作りです。しかも竹は自然の素材なので、一つ一つに個性があります。毎回同じやり方では理想の竿を作ることはできません。だから技術を磨くためには作り続けて、経験と勘を磨くしかない。毎回毎回が初めての勝負なのです。素材である竹を集めることから、選定、加工全てが自分の責任。それが竿作りの魅力だと感じています。

中村 直人さん

中村 滋さん
加賀竿工房 白峯
職人 中村 滋さん
加賀竿作りは工程が非常に多いですが、江戸時代から一貫して分業制にならなかったのは、竹の性質によるところが大きいとされています。
竹は乾燥させて火を入れて真っ直ぐにしても、漆を塗ったらその湿気でまた曲がります。曲がったらすぐに火を入れて戻さないといけないので、外部の職人に塗りに出すことができなかったのです。
そういう歴史からも、どの工程ももちろん大切ですが、やはり本体になる竹の扱いが加賀竿の根幹と言えると思います。また、竹は植物だから当然ながら一本一本曲がりやすさが違って、それぞれクセがありますよね。竿に適した竹、竿には向かない竹の見極めも大事な仕事です。
直人くんはまだまだ覚えることはありますが、釣りが大好きというのが大きなアドバンテージです。私どもが作った竿を使うのも釣りが大好きな人たちなので、使う人に寄り添った竿を作ることができるんです。まだまだ一人前ではありませんが、職人になればまた新たな壁が生まれる。それを乗り越えることができる人物だと感じています。
取材を終えて
加賀竿の工程数はおよそ120。しかも火入れした竹を落ち着かせる、漆を乾かすなど、制作工程の中に待つ時間が多いのが特徴だ。竹を取りにいくことから数えると、一本の竿が完成するのに3〜4年かかる。それが理由で職人の数も減り、後継者を育てるのが難しくなっている。取材中に師匠から度々言われたのが「若い職人でも、制作期間の長さや手間の多さに見合った報酬を得られる仕組みにしたい」という言葉。修業中の直人さんが、まだ技術が未熟ながら取材を受けてくれたのも師匠と同じ思いを共有しているからだ。取材中、常に感じていたのが、直人さんの体から溢れ出てくる「釣りが大好きで、竿を作るのが大好き」という感情。職人を目指すなかでこれからも様々な壁があると思うが、無尽蔵の愛をもっている直人さんならどんな困難でも乗り越えることができるはずだ。

加賀竿
江戸時代より石川県加賀地方に伝わる竹製の釣竿。
緩やかな川で毛針を使って釣る「ドブ釣り」の竿はドブ竿と呼ばれ、重さと堅牢さが特徴。当時加賀地方を統治していた加賀藩は幕府の監視が強く、表立って武芸の鍛錬ができなかったため、武士たちは重い釣竿を使用することで体を鍛えていたとされている。
明治になり、庶民が釣りをするようになると、堅牢さを活かした鮒竿なども作られるようになる。
戦後、加賀地方には30人ほどの職人がいたと言われているが、今は加賀竿の技術を受け継ぐのは中村滋さんただ一人。中村滋さんの3人の弟子が未来を担っている。